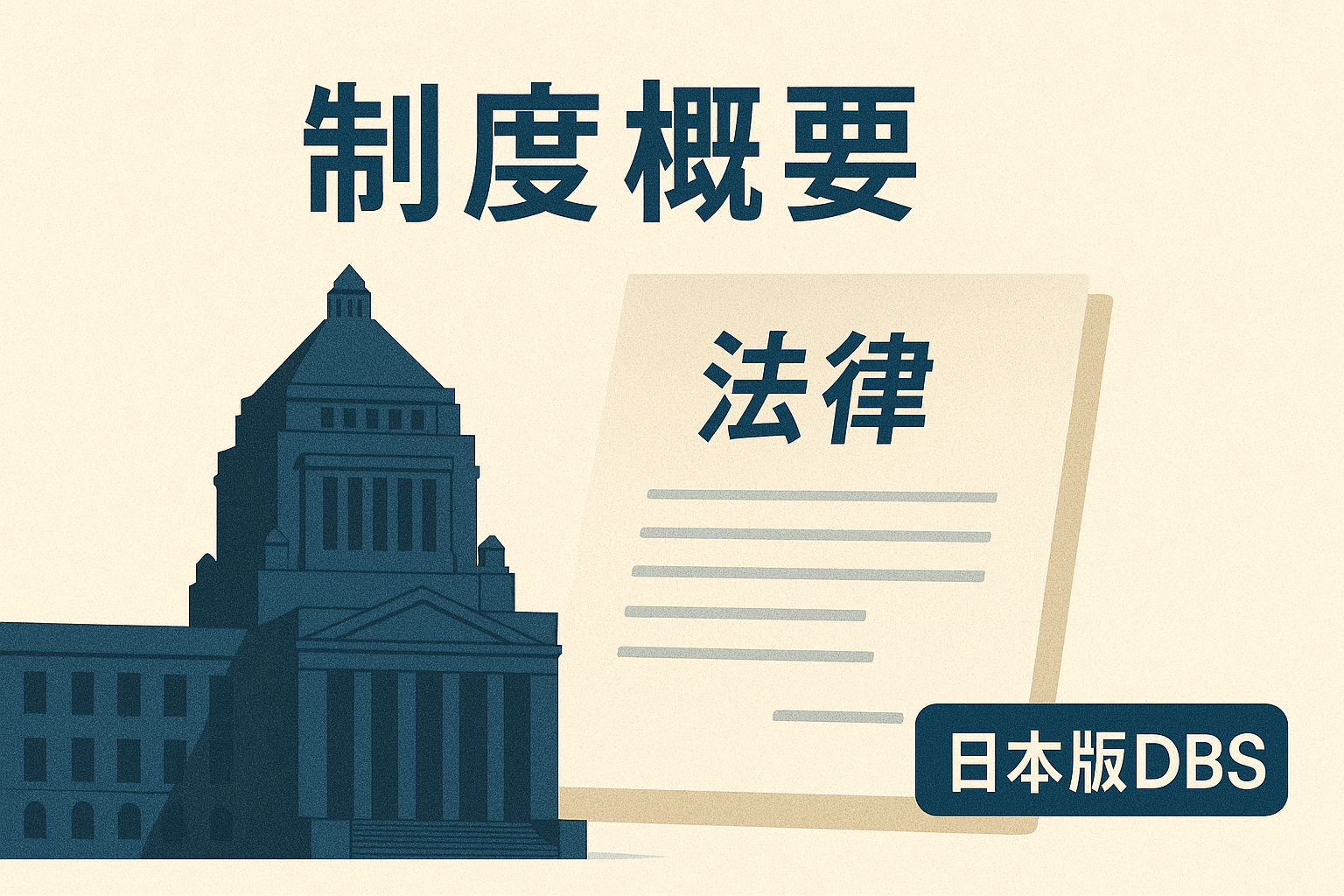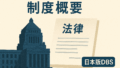なぜ「離職」の定義が重要なのか
こども性暴力防止法では、対象業務従事者が離職した日から起算して30日以内に、事業者は犯罪事実確認記録等を廃棄・消去することが義務付けられています(法第38条第2項)。
この義務違反には罰則が科される可能性があります。
しかし、短期間で雇用契約を繰り返す場合、一時的に任用関係が途切れても、すぐに同一事業者で業務に従事することが予定されている場合、その都度記録を廃棄し新たに確認を行うのは、事業者・従事者双方にとって大きな負担となります。
この負担を避けるため、法は特定のケースを「離職」に当たらないと整理する特例的な解釈を示しています。本記事では、その具体的内容を解説します。
離職に当たらないとされる三つの主要なケース
以下のケースでは、客観性を有する書面等に基づき、近い将来に再度同一事業者で対象業務に従事することが予定されている場合、「離職」に当たらないと整理されます。
有期労働契約の反復継続(会計年度任用職員を含む)
- 事由:有期労働契約を行っている者で、雇用期間等の終了後も対象業務への従事を継続することが、新たな雇用契約書等の客観性を有する書面で予め取り決められている場合。
- 公務員の例:会計年度任用職員等では、任期終了後に再度対象業務に従事する職に任用される場合も該当。
- 実務上の影響:契約更新の間であっても記録の廃棄義務が生じず、継続して確認記録等を保有できます。
公務員における人材交流等
- 事由:公務員における人材交流等で、一度任用関係が終了するが、その後再度任用され対象業務に従事することが予定されている場合。退職金の未支給等により明らかであることが条件。
- 背景:公務員の人事異動や交流により任用関係が形式的に途切れる場合があるが、実態として業務継続性が高いことを考慮した整理です。
短期雇用・ボランティアの反復継続
- 事由:ボランティアや都度短期で雇用契約を締結している者で、一定期間を定めて同一事業者に従事する可能性がある旨の書面を取り交わしている場合。
- 留意点:書面を取り交わす際、事業者は従事者に対し、雇用契約書ではないことや書面の趣旨を説明することが適当です。
予期せぬ再就職への対応:30日ルールの特則
- 上記のような継続性が予定されていない場合でも、離職日から起算して30日経過前に同一事業者で再就職した場合、元々予定されていた次の犯罪事実確認までの間、記録を保有し続けることが可能です。
- 条件として、事業者が記録の廃棄・消去を行う前に再就職が確定している必要があります。
事業者が記録を保持し続けることのリスクとメリット
- メリット(負担軽減):短期契約の切れ目ごとに記録の廃棄・再取得(戸籍等の再提出を含む)という負担を回避可能です。
- リスクと管理義務:離職に当たらないとして記録を保持する場合、事業者は期間中も個人情報として厳格な管理措置を講じる義務を負います。
- 目的外利用・第三者提供の禁止が適用されます。
実務上の対応とガイドライン活用の重要性
- 例外規定を活用する場合、事業者はガイドラインに基づき運用する必要があります。
- 有期契約者やボランティアに対しては、記録提出の趣旨・目的や情報管理の徹底を事前に書面で伝え、理解を得ることが重要です。
- 「離職」と判断した場合、30日以内に確実に廃棄・消去するため、紙媒体の焼却・溶解・適切なシュレッダー処理、電子データの容易に復元できない形での消去を行う必要があります。
この記事は、事業者が犯罪事実確認記録の廃棄義務を例外的に回避できるケースを整理し、実務上のリスク・対応策まで網羅しています。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。