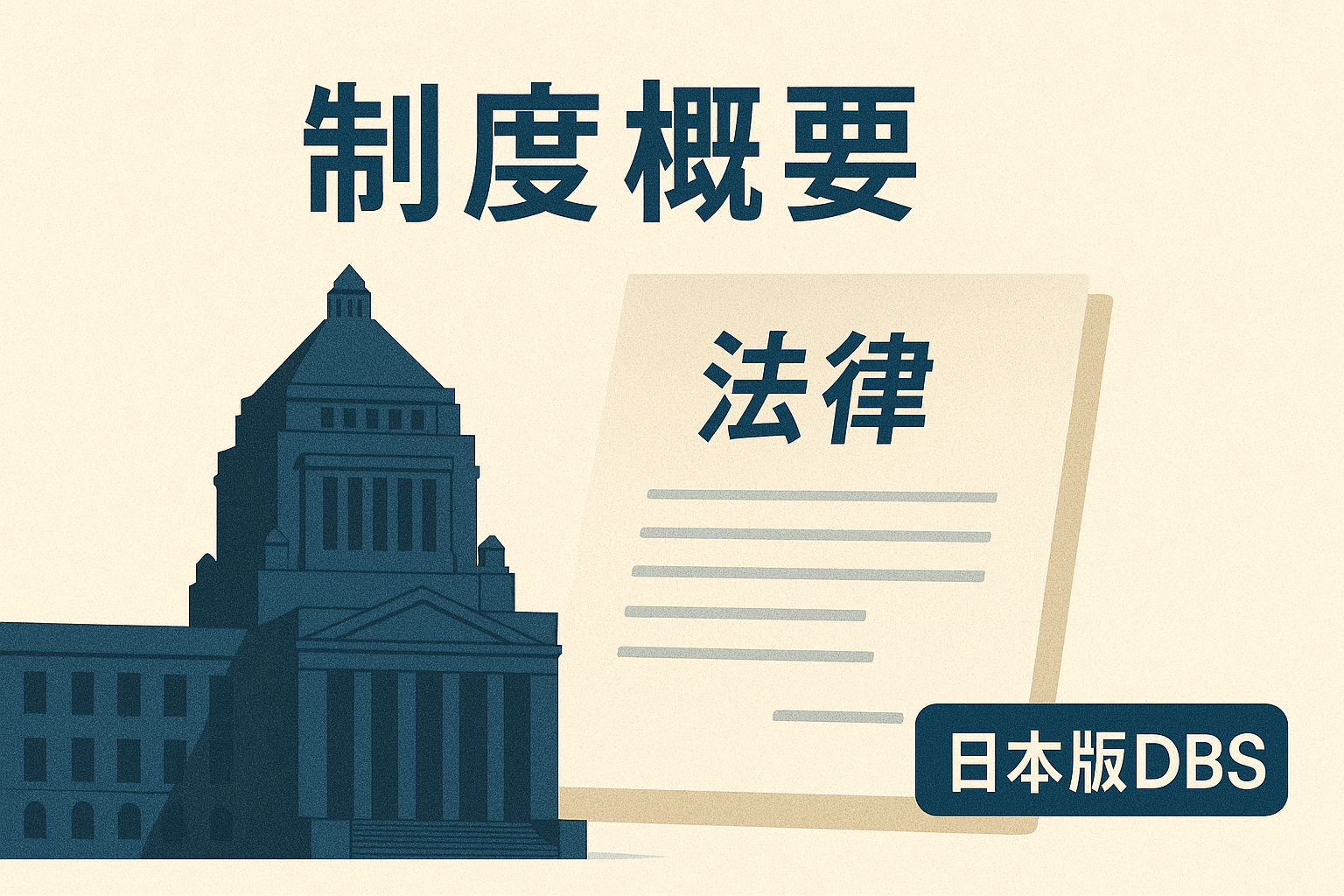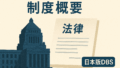犯歴「あり」と通知の重大性
こども性暴力防止法における犯罪事実確認では、法務大臣からの照会結果に基づき、申請従事者が特定性犯罪事実該当者と認められた場合の手続きが重要です。
この場合、こども家庭庁は、あらかじめ申請従事者本人に通知を行う義務があります。従事者は通知を受けた日から2週間以内に内容の訂正請求が可能であり、この**「通知を受けた日」**の解釈が、従事者の権利と事業者への確認書交付のタイミングに直結するため、非常に重要です。
通知の到達時期が抱える法的・実務的課題
従来の行政法上の到達時期の原則
行政庁の意思表示は、相手方が「現実に了知し、又は了知しうる状態」に置かれた時点で到達したと解されます。必ずしも現実に知る必要はありません。
また、デジタル行政推進法では、電子情報処理組織を用いた通知の到達時期について、「受ける者の使用する電子計算機にファイルとして記録された時」に到達したものとみなす規定が置かれています。
なぜ「閲覧可能時」とするのか
法第35条第5項に基づく訂正請求通知は、原則として従事者ポータル上での閲覧を想定しています。
行政は、従事者が実際に通知を閲覧するかどうかに関わらず、通知を知り得る状態に置かれた時点で到達と整理することが適当と判断しています。
そのため、従事者ポータルに通知が掲載され、閲覧可能になった時点で到達したものとみなすことが決定されています。
意図的な不作為と行政手続の停滞回避
従事者が通知を閲覧したかどうかを確認してから到達とみなす場合、閲覧を意図的に遅らせる可能性があります。
法第35条第5項では、通知を受けた日から2週間以内に訂正請求が行われることになっているため、実際の閲覧を確認するまで交付手続を進められない場合、犯罪事実確認書の交付が停滞してしまいます。
そのため、ポータルに掲載された時点で通知期間が自動的に起算される解釈を採用することで、手続の遅延を防ぐ効果があります。
従事者側の予測可能性と権利確保の措置
「閲覧可能時=到達」とする一方で、従事者が通知を知り得る状態を確保するための措置が講じられます。
- 予測可能性の向上
従事者が手続きを行う画面に、犯罪事実確認の流れや通知の仕組みを明示。 - 周知の徹底
ポータルへの掲載と併せ、従事者宛にメール通知を送信。 - 訂正請求機会の確保
メール開封が確認できない場合やログで通知未確認の場合には、再通知などの配慮を行い、2週間の訂正請求期間を確保。
まとめ:デジタル時代における迅速な情報伝達
- 通知の到達時期の解釈は、法務省への照会から事業者への確認書交付までのフローを円滑化するためのデジタル行政上の重要な工夫です。
- 「従事者ポータルに掲載、閲覧可能になった時点」を到達時期とすることで、手続の意図的遅延を防止しつつ、メール等で従事者の訂正請求権を保護。
- 事業者は、従事者にポータルを定期的に確認する重要性を周知することが不可欠です。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。