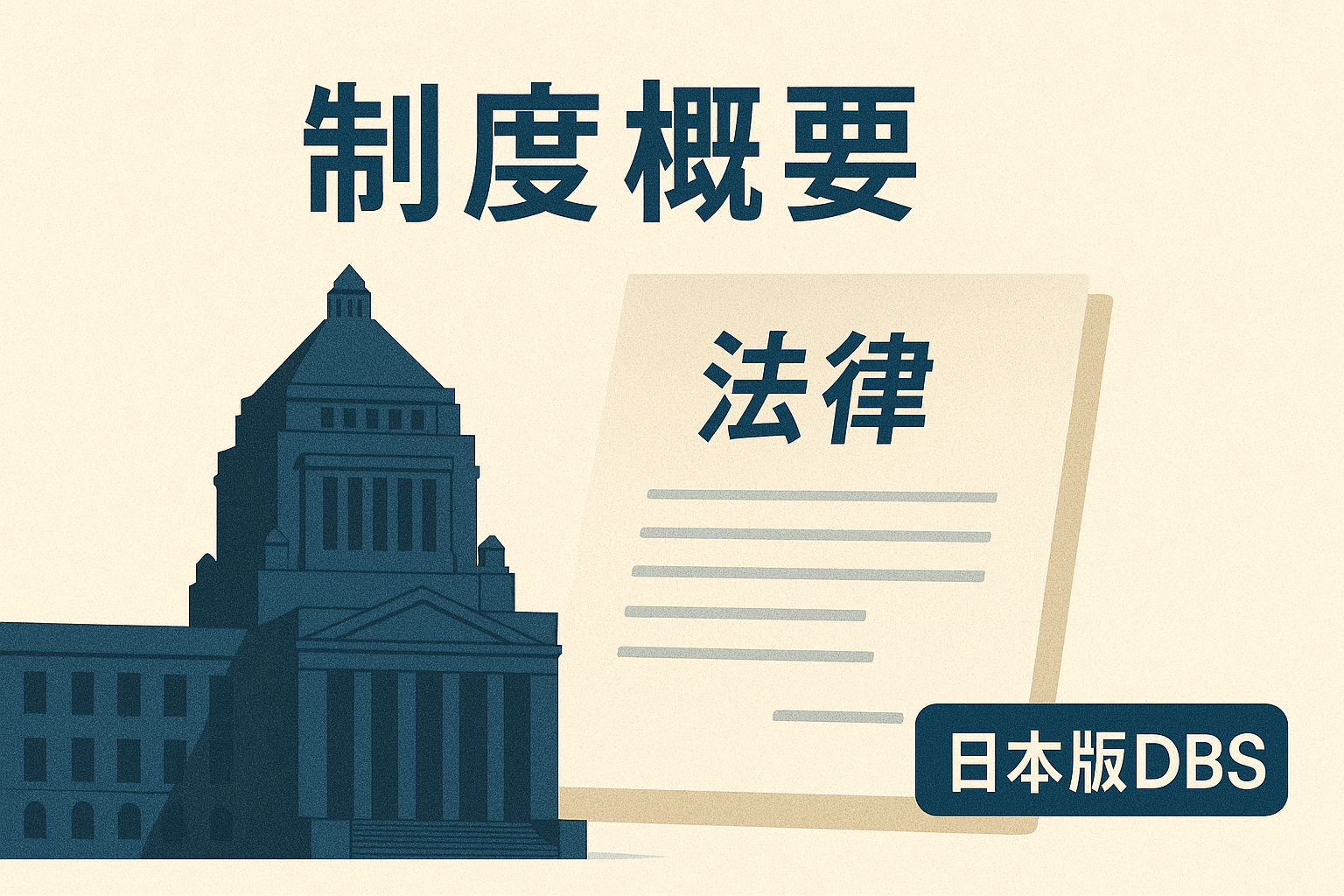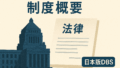はじめに
令和8年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」では、学校設置者等に対し、施行時に在職する教員など現職者について、犯罪事実の有無を3年以内に確認する義務が課せられています。
この「3年期限」は、法定期間内に確認を完了できなかった場合、公表や認定取消しといった重大なリスクを伴う極めて重要な要件です。
以下では、期限管理のための行政計画、人事上の対応、特定性犯罪事実該当者が判明した場合の留意点、そして機微情報の管理義務までを、実務の視点から整理します。
第1章 3年期限管理のための行政計画と事務負担の分散化
法定期限の対比と確認事務の分散スキーム
学校設置者等(義務対象)は、施行から3年間で全現職者の犯罪事実確認を完了しなければなりません。
一方で、民間の認定事業者等は「認定日から1年間」という別の基準で管理されます。
全国の学校職員等を対象に一斉確認を行うと、各自治体の事務負担が集中するため、国は都道府県立学校・市町村立学校の確認時期を約27か月に分散させる計画を示しています。
また、私立学校や児童福祉施設についても、所在地や設置主体に応じて確認時期をずらす方針がとられています。
施行後も続く犯罪事実確認の継続的義務
3年期限を終えた後も、犯罪事実確認は一度で完了するものではありません。
新たに採用する者や配置転換者については、業務に従事させるまでに確認を終える必要があります。
さらに、一度確認を行った者であっても、確認日の翌日から起算して5年ごとの再確認が義務付けられています。
これにより、継続的なチェック体制を維持することが求められます。
第2章 期限内に未確認者が生じた場合の違法状態の回避と人事上の措置
戸籍等未提出による期限切れリスクへの対応
従事者が戸籍謄本等の提出を怠ったまま期限を迎えた場合、事業者がその者を引き続き対象業務に従事させることは、犯罪事実確認義務違反となります。
この状態を放置すると、法違反による行政指導や認定取消し等のリスクが生じます。
そのため、学校設置者等は、期限内に未提出者がいる場合、速やかに当該従事者を対象業務から外すなどの配置転換措置を検討する必要があります。
業務命令違反としての懲戒処分の可能性
犯罪事実確認への協力(戸籍等提出を含む)は、職務上の義務に基づく業務命令と位置づけられます。
複数回の指導にもかかわらず従事者が提出を拒む場合には、業務命令違反として懲戒処分の対象となり得ます。
このような非協力的態度は、児童対象性暴力防止という法の趣旨に反する行為として、懲戒処分の合理性や相当性を判断する際に重要な考慮要素となります。
第3章 特定性犯罪事実該当者(現職者)が判明した場合の雇用管理上の留意点
現職者解雇の法的ハードルと防止措置の原則
犯罪事実確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であった場合、学校設置者等や認定事業者等は、その者を対象業務に従事させないか、その他の防止措置を講じなければなりません。
ただし、現職者の場合は既に雇用関係が成立しており、単に過去の犯歴を理由に直ちに普通解雇とすることは困難です。
特に、事業者が採用段階で確認制度の周知を十分に行っていなかった場合は、いきなり解雇に踏み切るのではなく、まず防止措置としての配置転換等を検討する必要があります。
雇用継続を前提とした防止措置の検討
対象業務からの除外は原則ですが、直ちに雇用関係を終了させる必要はありません。
事業者は、以下のような雇用管理上の対応を慎重に進めることが求められます。
- 対象業務以外への配置転換、または業務範囲の限定を行うこと
- 公務員の場合は成績主義の原則に基づき、人事評価結果を踏まえた転任先を選定すること
- 防止措置を円滑に進めるため、本人の意向を丁寧に確認し、可能な範囲で再就職支援を行うこと
これらの対応は、組織防衛と法的リスク管理の両立を図る上で不可欠です。
解雇の有効性の判断要素
配置転換などの代替措置を尽くしてもなお、事業所の性質上、防止措置を実行できない場合に限り、普通解雇が検討される余地があります。
ただし、その有効性が裁判で争われた際には、以下の観点が重視されます。
- 解雇が法の趣旨(児童対象性暴力等の防止)に基づく正当な措置であるか
- 措置の必要性や合理性が、客観的かつ社会的に相当であるか
最終的な判断は個別事案ごとに行われ、手続の適正さと本人への説明責任が極めて重要になります。
第4章 機微情報の厳格な管理と記録の廃棄義務
犯罪事実確認記録等の廃棄期限
犯罪事実確認に関する記録は、確認日から5年後の属する年度の末日から30日以内、または従事者が離職した日から30日以内に廃棄または消去しなければなりません。
これらの記録を外部業者に委託して廃棄させることは、第三者提供にあたるため認められません。
廃棄も含めて、事業者自らが責任を持って完了させる必要があります。
特定性犯罪事実関連情報の管理義務
防止措置の検討に際して本人から聴取した性犯罪に関する情報(特定性犯罪事実関連情報)は、犯罪事実確認記録と同様に厳重に管理する義務があります。
これらの情報が漏えいした場合、こども家庭庁への報告が必要となる重大事案に該当します。
情報管理は組織の信用を左右するため、法定管理期間の遵守とアクセス制限の徹底が不可欠です。
まとめ
学校設置者等に課せられる「3年期限」は、単なる形式的な確認義務ではなく、児童対象性暴力防止体制を根幹から支える重要な法的義務です。
期限を遵守するためには、初期段階からの計画的な事務スケジュールと、未確認者・特定該当者が生じた場合の迅速かつ慎重な人事対応が欠かせません。
法的リスクを回避しつつ、子どもたちの安全を守る仕組みを実効性ある形で構築することが、学校設置者に求められる最重要課題といえるでしょう。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。