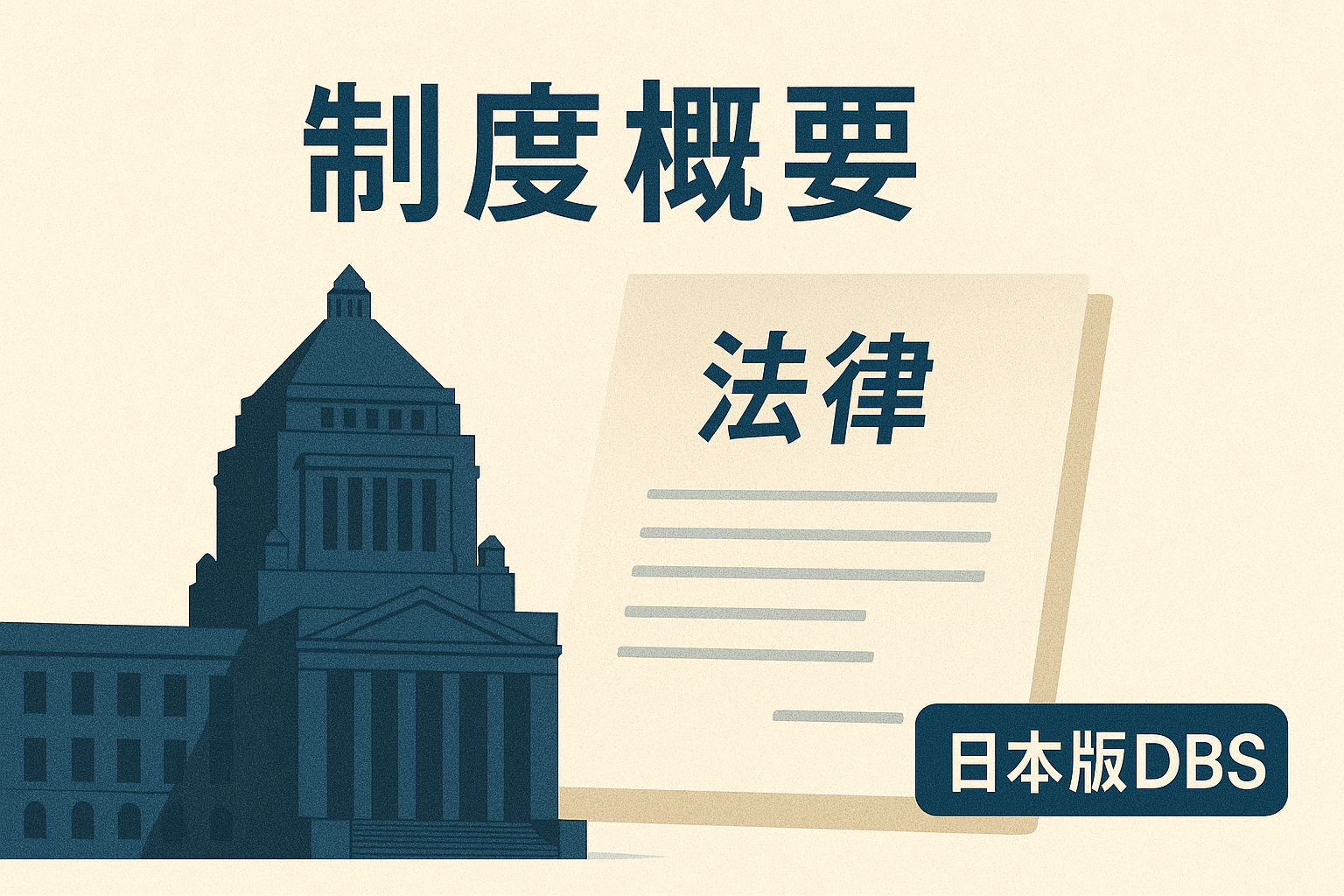機微性の高い情報の保護と法第12条の原則
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、性犯罪歴に関する情報は「犯罪事実確認記録等」として極めて機微性の高い個人情報と位置付けられています。
法第12条は、これらの情報を「犯罪事実確認または防止措置の実施目的以外」で利用・提供することを原則として禁止しています。
本稿では、この禁止規定の実務上の運用、特に保護者への説明対応や組織内共有のルール、違反時のリスクについて解説します。
保護者への「特定性犯罪事実の有無の回答禁止」と現場対応の留意点
禁止される行為の明確化
保護者から「特定の職員に性犯罪歴があるのか」といった問い合わせを受けても、事業者がその有無を回答することは法第12条違反となる「第三者提供」に該当します。
従って、いかなる場合でも個人を特定できる形で回答してはなりません。
情報開示が推奨される範囲
内閣府令・ガイドラインでは、事業者が開示すべき情報を明確に限定しています。
- 開示すべきでない情報:特定の従事者単位での確認状況(例:「A先生は確認済みです」)
- 開示が推奨される情報:職種単位での対象/非対象の区別、または「事業者全体として確認完了」といった組織レベルの開示
周辺情報から個人の犯罪事実を推測されるおそれがあるため、説明時には言葉の選び方や回答範囲に特に注意が必要です。
防止措置のための「目的内利用」の範囲と組織内共有のルール
目的内利用の定義
法第12条では、犯罪事実確認記録等の利用は「犯罪事実確認」または「法第6条に基づく防止措置」の実施目的に限定されています。
これを超える利用はすべて「目的外利用」として禁止されます。
組織内共有の具体例
- 教育委員会と学校の間で、配置転換など防止措置の検討に必要な範囲で共有する場合は目的内利用に該当。
- 特定性犯罪事実関連情報の取得(行為内容や本人の反省状況など)は、配置転換等の人事管理に必要な限度であれば許容されます。
ただし、共有範囲は「必要最小限の関係者」に限定し、文書管理台帳などで管理履歴を残すことが望まれます。
特定性犯罪事実関連情報の取得と「同意の任意性確保」の徹底
同意取得の原則
特定性犯罪事実関連情報は、犯罪の経歴に関する要配慮個人情報であり、本人の明確な同意なしに取得・利用することはできません。
この同意は「自由意思に基づく」ものでなければならず、面談などで心理的圧力が働かないよう配慮が求められます。
ガイドラインで求められる措置
- 同意の手続き厳格化:面談前に文書で目的と内容を明示し、同意書を取得。
- 利用目的の明示:主に「防止措置(配置転換等)を講じるため」である旨を説明。
- 不利益取扱いの禁止:同意を拒否したことを理由に人事上の不利益を与えてはならない。
- 情報の厳格管理:不要となった場合は復元不可能な形で速やかに削除。
これらを怠った場合、本人の権利侵害のみならず、事業者としての信頼失墜にも直結します。
共同認定・業務委託時における第三者提供の例外規定と実務運用
共同認定の場合
複数の事業者が共同で認定を受けている場合、一方の事業者が受領した犯罪事実確認書を、防止措置実施に必要な限度で他方に提供することが認められています(法第26条第7項)。
学校設置者と運営者の場合
学校設置者と指定管理者などの運営者との間でも、防止措置の実施に必要な限度での情報提供が可能です。
ただし、運営者の雇用職員の犯罪事実を学校設置者側が直接扱うことは想定されていません。
派遣労働者への対応
派遣先が特定の派遣労働者の交代を求める際、犯罪歴そのものを伝えるのは法第12条違反となります。
「防止措置を講ずる必要があるため交代を依頼する」といった、抽象的かつ目的限定的な伝え方を取ることが求められます。
目的外利用・第三者提供に違反した場合の重大なリスク
認定取消のリスク
認定事業者が犯罪事実確認記録等を不適切に利用・提供した場合、内閣総理大臣の判断により認定が取り消される可能性があります(法第32条第2項)。
これは、行政処分として最も重い制裁であり、再認定にも長期の影響を及ぼします。
罰則の適用
法第39条では、犯罪事実確認書に記載された性犯罪経歴情報を不当に他人に知らせたり利用した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
内部の一職員であっても対象となるため、組織としての内部研修とルール徹底が不可欠です。
まとめ:情報管理の厳格運用こそが信頼の基盤
日本版DBS制度の根幹は、「児童の安全確保」と「従事者の人権保護」の両立にあります。
事業者は、法第12条の原則に立ち返り、情報の取扱いを制度目的の範囲内に厳格に限定する必要があります。
適切な開示判断と内部統制の強化が、制度運用の信頼性を支える最も確実な手段です。
※執筆時点の情報です。最新の内容・詳細については直接お問い合わせください。
行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)
お問い合わせ先
TEL:096-288-2679
FAX:096-288-2798
MAIL:polaire@sp-pallet.net
※3営業日以内にご連絡差し上げます。
営業時間(完全予約制)
火・水・金・土:10:00~19:00
月・木:10:00~12:00
※日曜・祝日は休業日です。
※お電話でのご相談は行っておりません。
※ご依頼内容により必要な手続きが異なるため、「金額だけ」をお伝えすることはできません。必ず対面またはオンラインでお話を伺ったうえで、お見積りをご提示いたします。
夜間オンライン相談(完全予約制)
毎週水・金曜日:20:00~21:00(オンライン対応のみ)
※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。
ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。